新人研修の感想
2021年入社
配属1ヶ月後の感想

2021年度入社 M.T
研修は学ぶためのものであったが、案件はお客様がいたり何か作りたいというしっかりした目的を持って作業をしており、身が引き締まる思いであった。
研修で学んだことが基本になるのは確かだが、言語が違うしもともと研修でも遅れていたので会社に貢献できるかとても不安であった。
わからないということを共有できないことの方が問題であるから頼っていいと言っていただき、頼って、みよう見真似で作ったものが期待通りに動いた時はとても嬉しかった。
今もわかっていない部分は多く、たくさん迷惑をかけてしまっているが一人で立って歩けるように頑張りたいと思う。

2021年度入社 N.K
案件配属されてからちょうど1ヶ月経ちました。
先月7月まで新人研修があり、8月から初めて案件となります。
とはいえ自分が配属された場所では突然仕事の割り振りが始まる訳ではなく、この1ヶ月間は案件に向けた別の研修を行っていました。
内容としては、新人研修のときにメインであったJavaを言語として引き続き使用し、それを踏まえた上で実務での設計の考え方を学ぶことになりました。
新人研修の内容から連続しているところが大きかったためスムーズに案件研修の方に入ることはできました。
一方で実践を見据えた内容もあり、プログラムの設計方法がこれまでとは全く違っていたため驚きがありました。
今までは一つ一つのプログラムが短命で小さなものが殆どでしたが、大人数で長期間に渡り改修・保守を行うことが念頭にあると設計の組み方が変わります。
新しく学ぶことがあり面白いです。
来月から少しずつ案件に携わる予定のようであり、またプログラミングだけでなく要件の読み込みなどまた新しく学ぶことがありそうです。
少し緊張がありますが、学んだことを活かせればなと思います。
研修総合感想
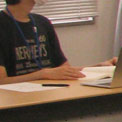
2021年度入社 S.O
4ヶ月間にわたる研修が終了しました。
研修内容のほとんどはjavaなどの技術的なもので、講義のスタイルをとるのではなく、課題を各々が進めていくというスタイルのものでした。
講義スタイルの場合は全員の進捗を合わせられる点や、習得する知識が個人間で乖離せずに知識の漏れを少なくできる点で優れているとは思いますが、各々が入社時点で持っている知識が異なることを鑑みると、課題を各々で進めていくスタイルの方が進捗を早められてよいように思いました。
課題については、自分でコードを書いた後に先輩社員にレビューをしてもらい、それを修正していくというサイクルで進んでいき、業務に適したコードの書き方を学べたように思います。
業務コードを書く際には、プログラムがとりあえず動けばよいというわけではなく、他の人が読んで理解しやすいかという可読性の観点が特に重要視されていると感じました。
研修に参加するまでは、プログラムは動きさえすればよいと考えていましたが、複数人で開発する際には可読性や拡張性など気をつけるべき点がたくさんあり、コードを書き上げた時点では問題がなくとも、後々大きな問題につながってしまうことがあるということを学びました。
また、技術的な研修と並行して先輩社員との面談や電話応対、ビジネスマナー研修や合宿、プログラミングコンテストや課題解決のための会議(KPT)などが実施されました。
技術的な面以外でも様々なことを学べるよい機会となっていたと思います。

2021年度入社 Y.S
新人研修が終わり、かなりプログラミングの知識がついたと思います。一応課題は一通り終えることができたのでよかったです。
JavaやJavaScriptで動的言語や静的言語の感覚を勉強して、HTMLやCSSでフロントサイドのあたりを勉強して、MySQLでデータベースの基本を勉強して、さらにプログラミングコンテストではアリゴリズムを考える経験ができて、インフラ課題ではローカル環境にサーバーを立ててみたり、いろいろな課題をたくさんこなしてきました。
さらに仮想案件ではKotlinやDartという言語について勉強して、SpringやFlutterというフレームワークも勉強できました。
なんだか今見てみるととんでもない量を勉強した気がしますがとても楽しかったです!
プログラミングの知識もたくさん増えましたが、他にもGitLab上でレビューをしあったり、リーダブルなコードを意識してコーディングができるようになったり、わからない部分や困っている部分について相談しあったりと、テキストではなかなか勉強できない部分についても学習できたのでとてもよかったです。
新人研修合宿の感想

2021年度入社 M.T
研修施設において、2泊3日の研修合宿が開催された。
合宿では、普段やっている技術的な研修ではなく、ビジネススキルに関する研修が行われた。
その中でも印象に残っている限定コミュニケーションと課題分析について感想を述べたいと思う。
限定コミュニケーションは、チャットツールによるディベートや、口頭によって図形を相手に伝えるといった、ツールが制限された中でのコミュニケーションを体験するといった内容であった。
ツールが制限されると、自分の意図した内容が正確に相手に伝わっているかの確認が難しいため議論が円滑に進まず、適切なツールを利用することの大事さをひしひしと感じた。
課題分析では、特定の課題に対して解決案を考え、どの解決案を選択すべきかを評価するまでの方法論を学んだ。
仲間とともに意見を出し合うことでうまくメソッドが機能し、良さげな案を考え出せた時は素直に嬉しかった。
こういった経験はなかなかこれまでしてこなかったので今後の糧にしていきたい。
研修以外では、3食おいしい食事が食べられたり個室が与えられたりと快適な生活を送ることができた。
やはり通勤時間が存在しないのは偉大である。
総括として、概ね充実した研修合宿であったと思う。この経験を今後の業務に活かしていきたいと思う。

2021年度入社 N.K
新人研修合宿に行ってきました。
本来なら5月頃に催される予定でしたが、新型コロナに関する非常事態が続き、7月14日にまで延期されてしまいました。
そんな中、千葉県船橋市にある研修施設で3日に渡る合宿が行われました。
研修内容としては、今までの技術研修とは異なり、日頃の意識や集団での課題解決に関する、実習を交えた講習がメインでした。
例えば、限定コミュニケーションという名前の課題では、テキストメッセージのみでチームで短時間で議論し結論を出すというものがありました。
これまでにもコードの提出やレビューなどで文章がメインのやり取りをすることが多かったのですが、相手の表情や声が分からない状況でのコミュニケーションは対面に比べてやはり難しいということを再認識しました。
ただ一方、会話のログが明確に残り、見直しもし易いという特性に助けられることもありました。
案件配属されてからはリモートでの作業が多くなり、人との文章のやり取りが増えることが予想されるので、メッセージを書くときの適切なバランス感覚を身に着けたいものです。
合宿の内容として他にも、『リーダブルコード』を各人が各章ごとに担当してプレゼンをする発表がありました。
コードの可読性を高めるには他の人の客観的な意見を知っておくというのが大事だと思うので、こうした意見を一度に聞ける会というは貴重でした。
そろそろ新人研修も終わり案件配属の時期かとソワソワしていますが、今回の合宿も含め新人研修で学んだことを配属後も無駄にしないよう頑張っていきたいと思います。
4月末時点での感想

2021年度入社 M.T
今日で4月が終了した。
研修内容・同期間の交流・私生活の3つの点から感想を述べたいと思う。
まずは研修内容だが、とにかくJavaとGitに慣れることから始まった。
プログラミングの知識はC言語に対する基本的なものがあったので最初のうちは問題なく進められたが、徐々に課題が難化していくにつれて未知の概念に触れることが多くなり、時間がかかるようになってきた。
もっと様々なコードに触れるなどして知識量や熟練度を増やしていきたい。
Gitに関しては完全に初めて扱うものだったので最初は戸惑ったが、とりあえず基本的な操作は習得できた。
git
worktreeなどまだまだ知らない機能が多くあるのでそれらにも少しずつ触れられるようにしたい。
同期間の交流に関しては、積極的に議論に参加したりお昼休みに一緒にプロセカをしたりと仲良くやれているので満足している。
個人的には、休日にもボードゲームをするなどの交流ができたら良いと考えているのでその辺りが今後の課題である。
また、4月の最終週から緊急事態宣言により在宅勤務が始まったが、これによりコミュニケーションを取る機会がやや減ったのでもっとdiscordを活用して積極的に絡んでいきたい。
私生活に関しては、通勤が1時間ほどかかるので平日にアニメを見るなどの時間があまり取れないのが少し残念である。
だが、ルーティンがしっかりと確立されることにより生活リズムが整うというメリットがあった。
これに関して、在宅勤務になることによりそのルーティンが崩壊して生活習慣が乱れるという事態が発生した。
入社2年目からは在宅勤務をメインにしようと考えていたので、在宅でも正しい生活リズムを作れるよう改善が求められる。
また、休日の過ごし方も昼過ぎまで寝ていることが多々あるのでなんとかしたい。
総括として、概ね満足した1ヶ月を過ごせた。
5月以降も今後の課題に取り組みながら充実した研修生活を送っていきたい。

2021年度入社 N.K
4月1日の入社式からちょうど1ヶ月たちました。
その初日に色々と会社の説明を受けた後、新人研修が始まりました。
この1ヶ月間で過ごした時間の殆どはその研修にあてられており、主に
Java の勉強を行いました。
私は Java
を今まで触ったことがなく、一から知識を入れていくことになりました。
ただこの研修で徐々にこの言語の使用やコードの書き方などに慣れてきました。
1ヶ月が経過した記入日現在では、自分で課題の問題に取り組みつつ、同期の人達と互いにコードのレビューをし合うところまできました。
同期の人たちと相談や議論をしながら技能を身につけられてきている実感があり、新年度始まりのこの1ヶ月はとても充実していたように感じます。
会社や先輩の雰囲気も、少しずつではありますが分かってきたように思います。
4月の半ばまでは平日毎日通勤をしていたのですが、緊急事態宣言が発令されたこともあり、4月最終週は在宅勤務となりました。
一人で作業するのは少し寂しさもありますが、リモートであってもうまくツールを使ってコミュニケーションが取れています。
環境の変化に大きく影響されることなく、この調子で研修で技能をどんどん身につけていければなと思います。
2020年入社
入社1年後の感想

2020年度入社 Y.K
インタープリズムに入社していつの間にか一年が経った。
入社後すぐに緊急事態宣言が発令され、リモートワークで研修することになったことをよく覚えている。
遠出などは未だ難しい状況ではあるが、それなりに充実した一年を過ごせたように思う。
この一年、仕事をする上で特に意識していたことは「人を頼る」ということである。
社会人としてはわからないことを質問したり、困っていることを相談するというのは至極当然ではあると思うが、今までの自分は人を頼ることに苦手意識を持っていたので、この課題は早く克服せねばと思っていた。
幸い、チーム内でも質問・相談しやすい環境づくりが積極的に行われていたため、安心して頼ることができた。
ただ、この質問の仕方は相手に負担が大きかったなぁと質問の後で思うことなども多いので、その辺りは改善していきたい。
次の一年の目標としては、自分のスキルを増やしていきたい。
今の案件でも自分にできる仕事はまだまだ限られており、もっとチームに貢献できるようになりたいという気持ちと、単純にいろいろできることがあるとかっこいいし嬉しいよねという気持ちである。
そのためにも、まだ経験していないことにチャレンジしていきたい。

2020年度入社 H.M
一年前の自分と比べると見違えるほどの成長を実感しています。
本当に何も知らなかった学生が毎日仕事をして、微力ながら案件に貢献していることを思うと自分で自分を褒めてあげれます。
入社や案件配属の際に不安に思っていたあらゆる事は先輩方や同期等のフォローに支えられて全く問題なく過ごせたかなと思います。
また業務後も自分なりに趣味を楽しめていたりして良い毎日を過ごせています。
社会の情勢に振り回されたりしましたが本当にとてもいい一年目だったと思います。
一方で今の自分が今の自分を見ると欠点だらけで一年前と対して変わってないように思えます。
研修中から小さなミスが多くて、1年たった今でもそれが直っていません。
案件でのコーディングのルールがあるからか、研修の時よりも小さなミスの指摘が多くなった様にさえ思います。
さらに単なる凡ミスが多いというだけではなくて、知識や経験に関してもまだまだ足りなく、自分と先輩方との間に途方もないような差を感じることもあります。
ミスが多かった日は少し落ち込みますが、来年の自分が今の自分と比べて驚くほどの成長を実感できるように無理なく少しづつ成長していきたいなと思っています。
配属1ヶ月後の感想

2020年度入社 H.T
8月から案件に配属された。
最初の環境構築から苦難の連続だった。
npmやNode.js、gulpなど、全然知らない知識が大量にやって来て、K先輩にしつこいぐらい何度も何度も質問したり、ネットで調べて見様見真似でやってみたりして食らいつきながら2~3週間ぐらいかけて何とか乗り越えた。
その後は先輩から具体的なタスクが振られるようになったが、そこでも最初は分からないことだらけで、小さな疑問でもすぐにK先輩に質問して、一つ一つ潰していった。
何の解説もない状態でいきなりソースコードを読んでもさっぱりだったが、大まかな意味をK先輩に教えてもらった後はだいぶ理解しやすくなった。
コードを書くタスクは今の所そこまで複雑なものはなく割と順調に進められているが、elasticsearchの使い方を調べるタスクはかなり骨が折れた。
というのも、今までのタスクは疑問点は先輩に聞けばよかったが、elasticsearchは先輩も知らない分野だったからだ。
疑問点は一つ一つメモしながら自分で調べて順番に潰していく作業の連続で、調べても分からずなかなか進まない事も多々あったが、根気強く続けた結果今では知識の大まかな整理はできたように思う。
振り返ってみると、僕が苦労したのはやはり、新しい知識を吸収する段階だ。
ここまでやってみて気づいたのは、全てを完璧に理解しようとせず、大雑把に「だいたいこんな感じ」ぐらいに理解して進める事の必要性だ。
僕はどうしても細かいところまで完璧に理解しようとしてしまうが、それをやってるといくら時間があっても足りないし、そもそも必ずしもそこまで理解する必要がない事もしばしばだ。
必要なところは今まで通り妥協せずに理解し、そうでないところはとりあえず受け入れて使ってみるというように、柔軟に対応する必要があると強く感じる。
また、「ただ言われたタスクをやるだけ」といった受け身な取り組み方はしないようにしている。
そのタスクに関連した+αの知識を自分から調べて理解を深めればより自分が成長できるし、「そのタスクはどういう背景で出て来たのか」「その機能はどういう使い方を想定しているのか」「なぜそういう仕様なのか」などを自分から聞けば、コードに活かせたりより多角的に案件を理解できる。
ただでさえ、K先輩は顧客との打ち合わせから後輩5人への広範囲に渡るタスク振りを全部一人でこなしているので、こちらとしても出来るだけタスクという機会を活かして技術面・案件面どちらも知識を習得して、協力できるようになりたい(それまではたくさん質問すると思います、、、よろしくお願いします。。。)。
最後に、僕はこの案件に配属してもらえてすごくありがたく思っています。
理由は、AIやグラフDBといった最先端の技術を学べるという事と、自然言語を解析するという事自体が自分の興味に合っている(外れていない)事、そして分からない事はいつでも聞けばすぐに教えてくれる先輩がいるからです。
特にK先輩には本当にしつこいぐらい細かな質問を何度もしてしまっていますが、いつでも親切に教えてくれて、本当に感謝しています。
毎日が過ぎるのが本当に速く感じる今日この頃です。

2020年度入社 Y.K
案件に配属されて早1ヶ月が経過した。
とはいえ、まだたったの1ヶ月であり仕事らしい仕事を任されるには至らず、そのための勉強に心血を注ぐ日々である。
しかし、それでも新人研修の頃とはいくつかの点で明確に異なる。
まず、これは当たり前のことだが、今までの業務中の関わりはほとんど同期だけだったが、配属後はチーム活動と通して先輩との交流が増えた。
関わるようになったのは同じ案件チームの先輩だけだが、先輩との接点が増えたことは嬉しい。
ただ、その分同期との交流が減ったことは少し寂しく感じる。
次に、プログラミングに直接関係しない案件特有の知識が要求されることである。
新人研修時はほとんどすべてがプログラミングに直結する内容ばかり勉強していたが、案件配属後は単に技術的な知識だけでなく、開発対象のサービス仕様の知識も身につけなくてはならない。
私の配属された案件は、案件説明会の時点から、覚えることが多いと釘を刺されていたが、実際その通りであった。
現在はサービス仕様について各々が勉強する以外にも、チームとしての勉強会が週一で開かれている。
最後に、新人研修のときの学習と比べて、より実践的な内容を意識するようになった。
教科書的な内容が役に立たないわけではない(もちろん役に立つ)が、配属後は「この現場ではどうするのか」ということを意識することが増えた。
案件に配属されて1ヶ月経ったとはいえ、まだまだ覚えなければならないことが山のようにある。
しかしこの1ヶ月で、このチームとしての活動にはある程度慣れてきたように思う。
私たち新人がこの案件で実際に仕事を割り振られるようになるのはもう少し先とのことだが、その日付はすでに告知されており、その期限は迫りつつある。
それまでに全てを覚えなければならないというわけではないが、できる限りの知識を技術を身につけ、チームに貢献できるようになりたい。
研修総合感想

2020年度入社 H.M
四ヶ月の研修が終わった。ひとつづつ振り返っていこう。
入社前からコロナウイルスの影響で在宅研修の告知があった。
初日は新人は全員出社だったが2日目から在宅ができるようにするためもあり研修はかなり駆け足だった。
その影響で翌日にはGitのエラーを起こしてしまって困った。
先輩方の助けがあって解決できたが、もしこの日から在宅になっていたら対処に時間がかかり、かなり研修がストップしていただろう。
入社当初、自分は事務所での研修を望んでいたが政府の緊急事態宣言発令とともに4月7日から在宅研修へ移行した。
出社は4日間だけでまだ不安が大きかったが案外すぐに(1日で)慣れた。
4月のKPTでは同期間のコミュニケーション不足と在宅研修での孤独を考慮してdiscordなどでの会話を伴うtryが多かったように思える。
そのおかげでコミュニケーション不全も起こさず、また同期間の交流もスムーズであったと思う。
これらのtryがあったからこそ、2ヶ月続いた在宅研修のデメリットをあまり感じなかった。
この後、研修中ずっとKPTの存在は学習を助けてくれるものであったと思う(途中暴走気味になったけど...)。
特にGitのwikiでの情報共有やdiscordでの勉強会がとても助けになった。
そして緊急事態宣言とともに始まった在宅研修は緊急事態宣言とともに終わりを告げた。
事務所での研修が始まるに伴って通勤が不安材料であったがこれも在宅研修と同じですぐに(3日で)慣れた。
事務所に通うことで同期と対面でコミュニケーションが取れるようになった。
これにより課題についての議論が在宅の時よりかなり活発になって学びが加速した。
これは在宅で黙々と勉強した時間があったからこそと思っていて、その意味でいい流れとタイミングだった。
研修のシステムや周りの環境について振り返りができたと思うので、次は具体的な言語の学習について振り返っていこう。
まずJavaで数字を三つ出力すると言う、所謂HelloWorld!的な基本文法から始まった。
最初はそれすらうまく書けなかったことが今では懐かしく思う。
その後はif、for、再起処理、クラスやその継承、インターフェース、clone、例外、ジェネリクス、ラムダ式など網羅的に?学んだ。
個人的に最初に躓いたのは、クラスとその継承を実装する課題であったが、その時レビュー担当の講師でもあったメンターさんに丁寧に何度もレビューしていただいたおかげで理解することができた。
Javaの課題に2ヶ月ほどかかったがその間に、社会人としてやっていくことやプログラミングをこれからも勉強していくことに対して、何か自信のようなものがほんの少し芽生えたと思う。
事務所勤務になって程なくしてプログラミングコンテストが始まった。
研修中は主に可読性を重視していたがコンテストに関しては可読性は不問、実行速度のみの評価だった。
今まで意識してこなかった部分だったので純粋に取り組むだけで得られるものが多かった。
順位としては振るわなかったが個人的には満足なコードが書けたのでポジティブにコンテストを乗り切れたと思っている。
Javaの課題が終わるとHTMLとCSSの課題が始まった。
Javaと全く違う雰囲気に始めは戸惑ったが少し作業するだけでサイト(みたいなもの)が目に見える形になるのでとても楽しかった。
HTMLはとても寛容に設計されていて文法的に間違っていてもうまく動いてしまうようなことがあって、そこを気をつけながら正しくマークアップしていくのが難しかった。
またJavaと違ってベストな書き方みたいなものがない場合が多くて、機械を意識したり人を意識したりの判断も経験不足ゆえなのか、とても複雑に思えた。
続いてjavascriptの課題。
javascriptもHTMLと同様かなり寛容に作られている。
そのぶん自分で型を注意してコードを書かないといけないなど制約が厳しい厳格なコードのありがたさにも気づけた。
jQueryを使って簡単なアプリを作る課題では学部の頃から頭の片隅にあったことを実現できてとても楽しかった。
データベース課題は、課題をこなして有用性などを頭で理解することはできたが、まだ実感が伴わない。
今後、業務で必要になった時に勉強し直すことになりそうだと思っている。
少し不安だが、一度勉強したことがあるのは次に勉強する時に大きく助けとなるはずだ。
インフラ課題に関してはJavaで芽生えたわずかな自信を根こそぎ摘み取るものとなった。
なんとか調べて勉強すればなんとかなるはずと思っていたが、結局は同期がまとめてくれたwikiにかなり頼る形で課題に取り組んでいることが多かった。
さらに、インフラの必須課題で研修期間内に取り組めなかったものもあった。
これが今後どのように業務に影響を与えるかわからないが、いい方向でないことは明白である。
案件配属後の不安がまたひとつ積み重なってしまった。
全ての研修をコンプリートすることはできなかったが、4月1日の自分と比べて想像もできないほどの成長を遂げたと思っている。
不安材料は今後の伸びしろと思って前向きに8月からの案件配属を待ちたいと思います。
これは完全に書きすぎだね。

2020年度入社 H.T
4/1に入社してすぐに研修が始まった。
いきなり大量の知識を教わり、その後は問題だけが与えられて「あとは自分で調べてください」というスタイルで、本当に面食らった。
しかし本当に辛かったのは、僕が分からないことだらけで何も進まない時に、周りの同期たちはすらすら課題をこなしていたことだ。
その時は本当に泣きそうになるぐらい辛くて、この業界を選んだのは間違いだったのかと思ってしまうほどだった。
でも、「分からないまま適当に誤魔化して進みたくない。遅れてもいいから一つ一つ理解しながら進もう」と開き直って、自分のペースで納得しながら進めていった。
初めの頃(A課題)は同期たちからだいぶ遅れを取っていたが、A課題をやり終えてJavaの仕組みを一通り覚えた後は、主にalgorithmを考える課題だったので、ある程度スムーズに進めて、気づいたら同期たちに追いついていた。
特にListやMapの擬似クラスを実際に実装してみたり配列をsortするalgorithmを考える課題は、難しかったが割と楽しかった。
次のPGコンテストは完全にalgorithmを考える課題だった。
動くalgorithmは書けたがメモリーエラーになってしまい、その方針ではどう頑張ってもメモリーエラーになるということに気づくのにかなり時間がかかってしまった。
方針を変えたらメモリの壁はすんなりクリアし、タイムも速くなりランキングは25位ぐらいに入れた。
しかし上位のタイムの方が桁違いに速く、algorithmによってはスピードに雲泥の差が生じるということがよく分かった。
だがまだ終わりではない。これからも時間がある時に考えて、もっと速いalgorithmで再エントリーするつもりだ。と書いてる今も考えている。
次の課題はJavaScriptだった。
やはりここでも最初の知識のinputにかなり時間がかかってしまった。
というのも、おそらく他の同期は課題をやるごとに調べて知識を身につけていたと思うが、僕は最初にtutorialを一通り読んで体系的に理解しようとしたからだ。
その結果また同期たちからかなり遅れを取ってしまった。
研修最後の頃にギリギリJavaScriptの必須課題を一通り解き終わったが、その後のサーバー構築やDBは全く手がつけられなかった。
振り返ってみると、大変だったがすごく充実した時間だった。
最初は分からないことだらけで、かつ同期に対する劣等感との闘いで、さらに一見”放任主義”のようにも見える研修のやり方にかなり不満を持ったのも事実だ。
が、やり終えてみると自分の得意不得意がはっきり分かって、むやみに劣等感を抱くこともなくなり、少し自信がついた。
さらに、自分のペースで自分が納得するまで課題に取り組めたのは、そのような研修のスタイルだったからこそだと思い直した。
大学までとは違い、与えられた教科書をただ理解すればいいという世界ではなく、分からなかったら本を買うなりネットで調べたり人に聞くなりして、能動的に解決する力が大事だということを教わった気がする。
最後に、忙しい中親身になって僕の質問に長い時間付き合ってくれたメンターのIさんや教育担当のMさん、講師の先輩方には本当に感謝しています。
ありがとうございました。
新人研修合宿の感想

2020年度入社 M.Y
新人研修合宿では、これまでに行ってきた技術的な研修とは一転してビジネススキルについて学んだ。
1日目は主に『7つの習慣』という書籍で紹介されている「成功」する(ここで言う成功がどういうものであるかは本の中で定義されている)ための方法・考え方を、自分自身と照らし合わせながら座学形式で学習した。
このような人生論や自己啓発に関わる本にはこれまでほとんど触れずに生きてきたので、新鮮な体験だった。
自分は必ずしも紹介された内容を鵜呑みにするべきではないと思っているが、それでも生きていくにあたっての参考として知っておくのは重要だと感じた。
2日目と3日目に特に存在感があったのは、答えを出しにくい問題に対し自分自身の考察やグループワークでの議論を通してどうにかして答えを構成する、いわゆるアクティブラーニングのような形式の研修だった。
2日目は与えられたタスクを完了するまでの時間を見積もることに挑戦した。
事前に見積もりの方法を教えられているわけではなく、また問題自体にも前提が固まっていない部分がある。
その辺りも含めて考えたり調べたりする必要があるのでかなり難しかったが、先輩方が見積もりをする際の考え方に触れることもできる良い体験だった。
3日目は与えられた課題をグループで分析し、実行可能性やコストなどの様々な要素を考慮に入れた上で解決策を導き出すことをした。
提示された課題に対処するにあたって何が障害になっているのか、課題の裏にある本当に解決すべきことは何か、などの様々な視点から課題にアプローチした。
課題を分析する能力は、業務だけではなく生きていく上でも重要だと思った。

2020年度入社 K.S
まず総括として、早期の開催を想定しているため新入社員が交流できつつ、これからの仕事に必要な資質や能力を学ぶ、もしくは気づけるようにそれぞれのプログラムが配置されており個人的にはとても充実した内容であった。
具体的には初日、自身、または他者との中で質の高い仕事をするための「7つの習慣」を聞く中で、自身にはシナジーを起こす行動力が足りていないと感じた。
その後の「制限コミュニケーション(1回目)」では、新人がフラッシュに親しむ目的もあるのかと思いつつ、コミュニケーションツールならではの、文章のみで自身の考えを正確に伝える事の難しさを実感する内容であった。
二日目と三日目の午前では同期がリーダブルコードの内容を発表してくれた。
合宿本来の日程では難しかったであろう、話す側・聞く側の知識や感覚が加わった深い発表(内容)になっていたと感じる。
発表の後の制限コミュニケーション(2回目)では、1回目から一転して、もしコミュニケーションが取れたとしても自身と相手の理解をすり合わせる事は難しいということを再確認できた内容であった。
二日目の最後には、自身に与えられた仕事を何日で完遂できるかを見積もる「工数見積もり」が行われた。
自身の経験のなさから残念な見積もりをしてしまったが、先輩方の工数設定の際の説明を考えると自身の一つ一つのタスクの実装速度を正確に把握することも大事だが、それと同じくらい与えられた仕事をどれだけ正確に細分し、具体的な工程がイメージできるかが重要であると考え、得るものもあった。
その点では本来の合宿日程で行うのは少し早いのかと思いつつ、配属後ではこのようなことを行う時間を取るのは厳しいのかと思う。
最終日では自身の発表もあったのだが、スライドに書く内容をうまく選別できず、また内容を補足するスライドを作るべきところを作らなかったことでスライドの作りが甘く、話の拙さは内容の理解の甘さを露呈してしまい恥ずかしい限りである。
最後のプログラムである「課題分析」では課題に対するアプローチを評価する方法を考える内容であった。
基本的にはアプローチに点数をつけていく方法であった。
アプローチの方法という質的なものを、点数という量的な評価を用いて言い換えるのは自身や他者を説得するのに非常に有効な手段であると同時に、この言い換える工程で失われているものがあることにも注意しなければいけない。
最初にも書いたが全体を通してとても充実した内容であったと同時に、昼夜に同期同士・先輩方が交流し、より親しくなる中で良い影響が出ていると感じた。
来年にもこれから入ってくるであろう新入社員の皆さんのためにぜひとも開催していただき、充実した時間を過ごしてもらいたい。
4月末時点での感想

2020年度入社 K.M
入社して1ヶ月が経ちました。
コロナの影響で入社式の次の日から在宅勤務になったので、ずっと家で黙々と研修の課題を進める生活でした。
大学にいた頃と比べて、住居は変わりましたが家で作業をするという状況があまり変化がなく、安心して取り組めていると思います。
毎日同期とdiscordで会話しているので、孤独感も感じず周りの状況を知ることができて良いと思っています。
先輩との面談でも研修や会社についていろいろ聞くことができてよかったです。
研修ではjavaをひたすら勉強していてそれなりに自分の思うようにコードを書けるようになってきたと思います。
オブジェクト指向のような、クラスを多用するようなプログラミング方法はこれまでの自分の経験ではしてこなかったので、新鮮で書くプログラムの幅が広がって面白いです。
案件で他の言語を使うようになっても本質的な部分で今学んでいることが役に立ってくれることを期待しています。
Gitについても仕組みを知ると面白くて、使いやすさや利便性を感じてきました。
バックアップファイルを大量生産して自分の作業ディレクトリが汚れるということがなく、コミットした内容の復元も高速で容易なのがとても良いです。

2020年度入社 H.M
入社一ヶ月が経ち研修生活にも慣れた。
新型コロナウィルスの影響で在宅研修となったが先輩たちや同期の助けもあり問題もストレスもなく日々を送れている。
在宅勤務で一番心配であった同期間の交流はかなり活発になされていると思う。
特に毎日14時からのdiscordが毎日続いているのが、これは在宅だからこそだと思っていて、事務所に毎日通っていたら全員で同じ話題を共有して話す機会はもっと少なかったと思う。
もちろんその分少人数でのコミュニケーションが少ないが、これは今後の課題であると思って5月は積極的に個人discordに突撃していきたい。(金曜に3人での勉強会が開かれているので少しずつ改善していくのかな?)
院生の時と比べて食を中心にかなり生活が改善されていてとても良い。
しかしその反面、通学のための歩きがなくなって運動量はかなり減ってそれを補う運動も外に無闇にでられない今では家で筋トレなどしかないがなかなか続かない。
つまり、ご飯が美味しくて運動しないので太る。まじでヤバイ。
一ヶ月java
を勉強して知識が増えてきた実感があるとともにまだまだ知らなきゃいけないことが多すぎて少ししんどくなってきた。
今のまま勉強は継続して、この先はコードを書いて、体で覚えながら学んでいくことも取り入れていこう。
2019年入社
入社1年後の感想

2019年度入社 N.Y
研修半年、案件着任半年という一年を通して多くの知識を得た気がします。
先輩方に比べればまだまだ足りないものだらけではありますが、個人的には満足のいく成長であったと思います。
研修では主にjavaを扱いました。
案件では主にphpを扱っています。
言語が違うので一からの学習になるかと思いましたが、似た構造や考え方の部分もあり、研修で学んだこともいかせているなと実感します。
案件に着任してから使用することになった言語は研修とは違うものが多く、初めてのプログラマーとしての仕事であったことも相まって最初は随分役立たずだったと思います。
仕事が遅い上に間違いも多く随分迷惑をかけていると思います。
少しずつ案件の内容やプログラム構成の仕方などの手ほどきを頂き、まだまだ指摘される問題点は多いですが、最近は随分マシな仕事になってきたのではないかと思います。
もうすぐ後輩が入社します。
後輩が案件配属となる半年後までに、また少し成長できたらいいなと思います。
また、仕事とは関係ありませんが、案件についてから同期との交流が大きく減りました。
リモートや事務所以外の案件の配属により、さらに顔を合わせることが減りそうです。
個人的にですが、仲間がいるという感覚は何かしら支えになると考えるので、交流の場を定期的に儲けられたらいいなと考えています。

2019年度入社 Y.S
早いもので入社してから一年が経過しようとしている。
会社に勤めるということについて学生の頃は漠然とした印象しか抱いていなかったが、なんとなくどういうものか掴めてきた。
最初は毎日8時間の勤務や通勤を繰り返すことができるか不安であったが、ある程度期間が経つにつれその点は慣れたような気がする。
研修初日にはほとんどのことが初めてであり、今でも新しいことに取り組む際はわからない事だらけであるが、当時とは違いある程度なにを調べるべきか、どういうアプローチで取り掛かるべきかの手がかりは掴めるようになってきたと思う。
自分は今のところ研修後の初配属から配属場所の変更はされていないが、新年度を迎え新たなプロジェクトに取り掛かるようになった。
先輩方も知らない新しい技術を用いたり、よりお客様に近い立場で物事を考えたりするなどこれまでとは異なり本格的に自分の力でプロジェクトを進めていく様になるであろう。
その分伴う責任も大きくなるわけだが、年次を重ねるにつれ経験していく道だと思うし、今後自分がプロジェクトを引っ張っていく立場になるためには必要な能力だと考えている。
さて、ついに初めての後輩社員が入ってくる。
例え自分のプロジェクトに参画しないとしてもFace to
faceなどで関わることになるのだから、彼らが会社や仕事のことで困っていることがあるのならばそれを軽減させられるように接していきたい。
配属1ヶ月後の感想

2019年度入社 S.K
案件配属後1ヶ月が経ちました。
グラフDBに関する案件に関わっています。
言語はKotlinとTypeScriptを使っています。どちらも初めての言語でしたが、研修で学んだJavaやJavaScriptと関係があるので、基本文法などの習得はスムーズにできていますが、Vue.jsなどのフレームワークに苦戦しています。
実装は先輩社員に教わりながらしています。自分一人ではエラーの原因がわからなかったり、何をしていいかわからなくなることが多いですが、
1日でも早く戦力になれるように頑張りたいです。
またグラフDBについてもよくわかっていないので、勉強したいと思っています。

2019年度入社 Y.O
配属されて1ヶ月が経ち、ようやくプロジェクト全体の方針がぼんやりと理解できたような気がします。
配属された案件はサービスが3つあり、おおよそ同じ処理をするのですが、各々で別の処理やメソッドがあるため、なかなか理解することが難しく感じます。
そのため、1つのことをやった後に、次に別のサービスについて見ると異なっている部分がすぐには分からず、頭の切り替えがついていかないこともあります。
今のところ、プロジェクト全体の観点や特定のサービスの観点や、他の処理との兼ね合いから「こうあるべき」という判断はできません。
また、理解が足らない部分があるため、質問や現状報告の際にうまく表現できないことがあるのが問題です。
そこで、分からない部分があればその度に少しづつ先輩に質問して、それぞれのサービスの特徴を理解に努めたいと思います。
使用している言語やツールには少しずつ慣れてきたので、手すきの時間にそれらの勉強もしたいと考えています。
研修内容とはガラリと変わり、まだまだ戸惑う部分が多いですが、新しいことを知る絶好の機会だと捉えて、プロジェクトの理解を進めたいと思います。
研修総合感想

2019年度入社 A.K
5ヶ月の研修期間が終わり、とても勉強になった。
長期間、研修させていただいた会社とわからないことを教えていただいた先輩方にはとても感謝している。
研修の内容と取り組み方でわかったことがある。
研修の内容についてわかったことは、自分は知らないことが多いということである。
私は、大学の授業や研究でプログラミングを経験していたので、当初はプログラミング(Java)の研修は余裕があり、取り組んだことのないデータベースやインフラ関係を重点的にやりたいと考えていた。
しかし、実際はJavaの段階で知らないことばかりで苦労した。
特に、クラス、Map、可読性、計算効率など聞いたことはあっても知らないことばかりだった。
最後のインフラ関係の研修は、自分が一番やりたいと思っていたことだったもののやはりわからないことが多く苦労した。
課題は半分ぐらい終わらずまだやりたい内容があるので今後個人的に勉強していきたい。
ちなみに、苦労した研修のなかでもうれしいことはあり、サーバーを構築して外部のPCからアクセス可能にすることができた時は達成感を得られた。
研修の取り組み方については複数人で勉強することの良さを理解できた。
同期と話し合いながら学習していくことで、わからないことをすぐ聞けたり、気づかなかったことに気付けたりすることが効率的だった。
これは、これまででは一人で勉強や研究をやることが多かったので気付けなかったことであった。
研修でわかったことを今後の業務の中で生かせるように努めていきたい。

2019年度入社 Y.S
四月から5ヶ月間続いた研修が終わった。入社当初はプログラミングについてほとんど何もわかっていない状態であったが、研修を通して少しづつではあるが自分の組んだコードでプログラムが動く様子が確認できて力がついたのを実感した。
研修は大きく分けて、Javaとhtml/CSSとJavaScriptとDB(データベース)とインフラであった。特に、Javaに研修期間の多くを費やした。
Javaでは、コピーの種類や継承、オブジェクト指向などの概念の理解が難しかったが、最後には目的に応じたクラスの実装まででき、一番理解が進んだ。また、プログラミングコンテストではこの言語を用いた課題を行なったが、なかなか思うようにはいかなかった。
html/CSSでは自分の書いたコードがブラウザに見える形で表れたので、細かい調整に難儀したが、やってて楽しかった。昔ホームページを作った時にも少しやっていたが、その頃と比べてもかなり進歩してたように思えた。
JavaScriptではJavaとの違いが興味深かった。スコープやprototypeなどは気をつけないとハマるポイントであるので注意したい(最も、最新のバージョンではハマりにくくなっているような仕組みにはなっているが)。
DBとインフラはどちらかというと知識の習得に終始して実践は触りだけであったが、仮想マシンとの通信ができたのは達成感を感じた。
この知識がどこまでこれからの業務に役立つのかはわからないが、課題を通して苦しみ調べた経験は武器になり得るのではないかと思う。今後も新たな知識の習得に努めていきたい。
新人研修合宿の感想

2019年度入社 Y.S
これまでのプログラミングとは違った観点で研修を行うということで、どういうものなのか気になりつつ研修合宿を迎えた。
合宿する場所は、我が家から遠く開始時間もいつもより早いので結構早く家を出ることになった。
研修の初日は、七つの習慣という成功者の習慣を題材にした本についての講義を聞く(たまに実践する)のが中心であった。
習慣の内容は、当たり前に思える(が、当たり前にやれない人が多い)ことが中心だったが、中には今後の業務で実践したいと思えるようなものもあった。
二日目の午前中は、新入社員が全社会議で発表する自己紹介スライドの事前発表を三日目と分割して行なった。
私の他にはSさんとYさんが発表したが、それぞれ特徴的な発表をしており、御二方について知れることが増えてよかった。
自分の発表については、時間が思ったよりかかってしまいやや割愛せざるを得なかった一方で、発表の内容についてはそこまで悪くなかったとのことでよかった。
指摘を受けた点を改善して本番の発表に臨みたい。
その他には、今後の業務内容をもとにした抽象的な題材についてそれをこなすのにどれ位かかるかの時間の見積もりを行なった。
同じ題材なのに人によって見積もる時間が(最悪1日と一年くらいに)大幅にずれているのは興味深かった。
おそらくこの技術は年次を重ねるとともにリアルな値に近づいていくのだろう。
最終日は、残りの三人(Kさん、Kさん、Oさん)のスライド発表の他に、課題分析を行なった。
課題についていくつかのステップを踏んで解決するよう取り組んでいく内容だったが、自分とは違う視点での解決策も多く、それらを数値で順位づけをしてどの解決策が最善か決定することは大事だと思った一方で、本当にその点数でいいのか不十分なところも見受けられたように感じた。
三日間の研修を通して、様々な新鮮な体験をできたのはよかった。
一方で、開催時刻や日程、場所についてはどうしても難しいところがあるだろうが、もう少し工夫してくれたら嬉しいと感じた。

2019年度入社 S.K
研修合宿では普段のプログラミング研修とは違ったビジネススキルを勉強しました。
特に印象に残ったプログラムは限定コミュニケーションと課題解決解決手法です。
限定コミュニケーションではflashを使いテキストのみの討論をしましたが、身振り手振りなどを交えて直接コミュニケーションを取る時と違い、
文章の推敲に時間がかかってしまったり、文章を書いていると途中に同じ意見が出されたりと、上手くいかないことが多々ありましたが、この体験により
テキスト討論の難しさや、直接コミュニケーションを取ることの利点などが理解できたように思います。
課題解決手法では、与えられた課題についてチームで話し合って、問題点と解決策を出し合い議論しました。
特に解決策を数値で評価し結論を出すことが
難しかったですが、数値などを使って客観的に議論をすることの大切さや難しさが学べ、とても良い経験でした。
4月末時点での感想

2019年度入社 N.Y
1週目はPCについてもGitについてもjavaについても全くちんぷんかんぷんでどのように手をつけていいかわかりませんでした。
周りの方々(先輩や同期)にたくさん教えていただき、なんとか自力で調べながら進めるようになりました。
プログラミング経験の有無という意味で自分が一番出遅れていると思うので常に焦りを感じる一ヶ月ではありましたが、充実した日々を送れているという点では喜びを感じています。
研修の中身だけでなく、KPTやface
to
faceなどでメンタルケアにも気を使っていただいています。
手厚い補助に助けられていると感じます。
周りの方々ともだんだん打ち解けてきており、とても働きやすい(まだ研修ですが)環境だと感じています。
継続してモチベーションを保っていきたいです。

2019年度入社 Y.S
インタープリズムに入社してから一ヶ月が経過した。初日の入社式では、本当に自分がこれから社会人として働いていくのかという実感がわき新鮮な気持ちになると共に、これからついていけるか不安であった。
この一ヶ月は(今後数カ月もそうであるが)研修期間であり、専用の課題を解くことでプログラミングの基礎を学んでいく形であった。
最初に課題を見たときは、自分がほとんど未経験だったこともあって聞いたことのないような用語が並んでおりこれらの概念を一気に習得していくのは骨が折れるように感じられた。
しかし、同期の人たちと相談しあうことで自分一人では分からなかったことも分かるようになり、現在研修で使っているJava言語への理解も多少ではあるがついてきたような気がする。
分からないことを相談し合うことは、研修だけではなく今後の業務でも幾度となく行われるであろう行為なので、今後も継続していきたい(さらに、同期だけでなく上司の方々にも質問できたらいいと思う)。
まだ入社して一月ではあるが、生活リズムを含めて今後も今のスタイルを続けていきたい。
2018年入社
入社1年後の感想

2018年度入社 T.K
案件についたばかりの時は業務の全体像がつかめないまま、自分の作業が何のためのものなのかも理解できないままに、とりあえず指示されたことをやっていた。
言語もツールも知らないものばかりで、今思えばなんでもないようなものもすごく難しく感じていたように思う。
案件についてから半年ほど経って、ようやく業務の全体像がつかめてくると、当時の自分の作業がいかに非効率だったか無意味だったかと思うこともある。
半年の中で、インフラだったりrailsだったり、色々なことに触れることができたが、どれもわかった気になれないまま違うことを始めてしまい、なかなか頭がついていかず辛いと思うこともあった。
案件に着任してから、今では多少知識が増えているはずではあるけれども、変化がゆっくり過ぎて実感は少ない。

2018年度入社 Y.I
遂に自分の入社式から1年が経過しました。
正直なところ、入社式中に誰がどんなことを話していたかは覚えていませんが、自分で働いてお金を稼ぐという期待としばらくは研修とはいえ、仕事をやっていけるのかという不安があったことは記憶にあります。
1年も経てばそういった期待や不安は小さくなってきたものの今まで漫然と送ってきた人生を本格的に考えていかないとなぁ、という別なものが少しずつ台頭してきた感じです。
案件に配属してそれなりに時間が経過しての感想としては、言語の仕様そのものの難しさも然ることながら"良いプログラム"を書くことの難しさを痛感しています。
自分が書いたものよりも良いとされる書き方を後から知ることもあり、まだまだ経験と知識が必要に感じます。
生活面では、ちょっとダレて来ましたね。
去年は人生初めての一人暮らしということで自炊も頑張ろうかと思っていましたけれど、最近はその回数が見るからに減って来ています。
入社2年目になると言うことで、新入社員の方たちにとっては良き先輩になるとともに入社してから培ったことを元にして技術・経験・知識を増やしていきたいと思います。

2018年度入社 T.Y
10月はメールツール分析支援の案件に就きましたが、環境構築に手間取って1週間くらいそれに時間を費やしてしまっていました。
ですが、ここで苦労したからその後の案件で環境構築が苦にならなかったと思います。
11月〜12月は部品レイアウト自動化システム開発支援の案件に就きました。
それまで主に使っていた言語はJavaでしたが、ここでの開発言語はPythonで新鮮でした。
1月〜3月はコンサルティング支援ツール開発技術支援案件に配属されました。
この頃くらいから、自分には難しいと思ったタスクもできて、プログラマーとして自信がついてきました。
また、クライアント側もいじっていて、自分がした変更が見えて面白かったです。
ただ全体通して、1つのプロジェクトについている期間が短かったので、何かしらスキルが身についたのかわからないです。
研修総合感想

2018年度入社 Y.I
とうとう研修も終わり配属先が決定しました。
研修の期間としては長かったですが、感覚としてはあっという間でした。
大きく分けてJava、JavaScript、MySQL及び仮想OS上でのサーバ構築を行いました。JavaやJavaScriptでは入社以前に想像していたプログラミングという感じのもので与えられた課題に対して完成形に向けてロジックを組み立てていくのは楽しくもあり、初めのうちは可読性・保守性とパフォーマンスの考慮などは難しく感じました。
その他に、ソース管理という入社以前は特に馴染みのなかったものも使いこなせるようになったとは言えないまでも必要なことは身に付いたと思います。
半ばから後半にかけてはデータベースという、単語は知っていてもその実態はよく知らないものに関する研修でした。
MySQLを用いた研修でしたが、これはJavaなどと違って完全に聞いたこともないようなものでした。
関係モデルに基づいたデータ構造を持つデータベースからデータを取り出す、あるいはデータを入れておくテーブルを設計するといった一味違う内容でしたが、これはこれで楽しいと感じられる内容でした。
最後に取り組んだものは仮想OS上にサーバを立てるというものでした。
これは論理的に何かを構成するというより使いたいものを目的に向かってきちんと動くように設定する、という感じのものでした。
バージョンやディレクトリ構成の違いを自分の環境と比べながら正しく構築しきちんと動くようになった時はなかなか達成感がありました。
研修を終えて思うことは、まだまだ知らない技術や知識だらけだというこということです。
これから先は研修でなく業務を通じて、という形になりますが、貪欲に知識を吸収していきたいです。

2018年度入社 S.W
9月で研修を終え、来月から実際の案件につくことになる。
約6ヶ月もの間、研修に時間をかけてくれた会社には感謝している。
大学の講義でプログラミングを少しかじった程度しか経験のない自分にとってこの研修はとてもありがたかった。
研修は最初Javaから始まったが、初めて触る言語ということもあり、少し苦労した。
アクセス制限のチェックや内部クラスについてなど、面倒な課題もあったが、実際に自分でコードを書いて確かめてみるのは意外な発見等もあり、よかった気がする。
またリストやマップなどのデータ構造も実際にコードを書いて実装できた時は結構嬉しかった。
Base64のエンコーダーとデコーダーの実装も細かいbit操作で苦労したが、完成した時は達成感があった。
Javaの研修は結果的に3ヶ月かかり、予想進度より遅れてしまったがじっくり取り組めてよかったと思う。
どちらかというと調査系の課題より、具体的に何かを実装せよという課題の方がやってて楽しかった。
7月の頭くらいからHTML,
CSSの課題に入った。思った通りのレイアウトにならず、何がいけないのか調べるのに時間を取られたが、実際にサイトの外装ができた時は嬉しかった。
7月後半あたりからJavaScriptの課題に入った。
クラスベースのJavaとの違いに戸惑ったが、プロトタイプを理解したあたりからそれなりに楽しくなってきた。
また電卓やアニメーションなど目に見える成果物が出来た時は達成感もあった。
8月の初旬からはMySQLの課題に入った。
MySQLの課題はあまりレビューが受けられなかったこともあり、良い書き方というのがよく分からないまま終わってしまった。
インフラ課題も最後少しだけ残ってしまったのは残念だが、今ままでよく分からなかった概念が実際にやることで、少し理解できたような気がしてよかった。
家のPCでも色々試して見ようと思った。
6ヶ月長かったがかなり有意義な時間を過ごせたと思う。

2018年度入社 K.S
6ヶ月という長い研修の中では数多くのことを学びましたが、これで一人前のエンジニアになれたという実感は全くなく(現時点でそうなることは求められてもいない気がしますが)、まだまだ知らないことが圧倒的に多いのに果たして業務が務まるのかという不安の方が大きいです。
比較的長い期間を費やして学んできたJavaでさえ、まだ表層をなぞっただけという感覚なので、これ���らの実業務の中でさらに学び、知識や技術を身につけなければと思います。
HTML,
JavaScript, MySQL,
インフラに至ってはまだ体験版をプレイしただけという感じで、これからが本当のスタートだと思います。
この研修を通しての大きな収穫は、自分の思考の傾向と弱点を知れたことです。
他の新入社員はみな数学を専攻してきたこともあってか、「論理的に考えて、自分の頭の中に体系を組み上げていく」ことがとても上手いように感じました。
自分はどちらかというと論理よりもイメージで物事を掴みたがる傾向があり、この会社に入社するまではそれほど不便に感じたことがなかったのですが、プログラミングとの親和性はやはり前者の方が圧倒的に高いと感じました。
生まれ持っての部分も大きいと思うのでどこまで出来るかは分からないですが、少しずつプログラミング向きな思考回路を組み上げていくことを、今後の目標にしたいと思います。
新人研修合宿の感想

2018年度入社 Y.I
合宿の内容を振り返りながら感想を書いていこうと思います。
まずは初日について、施設に着いてある程度の準備を終えると研修を始める前に軽いIcebreakが行われました。
内容は気軽に考えられるものであり、普段は話す機会の少ない先輩上司方に対する緊張をほぐす良いワークショップだったと思います。
その後、ビジネスに対する一考えとして本を元にした”7つの習慣”に関する解釈や考察を聴講しました。
普段は意識しているようで明確には意識していないような考え方や行動の規範について認識を改める、ないしは新しい視点を得られたように思います。
中でもビジネスにおける勝ちや負け、ビジネスパートナーとの関係性について実体験を元にした考察やwin-winな状況に至るまでの経緯などのパートが面白かったです。
発想の転換、相手の明示的な要求の裏にある本質的な要望の読み取りなどプログラミング技術の研鑽をしているだけでは意識することのない思考のテクニックを知ることが出来ました。
いわゆるビジネス本に対してあまり好い印象は持っていないため、聴いている最中に眠くなるのでは、と懸念していましたがあまり興味が湧かなかったパートも含めて最後までキチンと聴けました。
また、途中に休憩がてらに平面図形を口頭で他人に伝えて自分の見ている図形を他人に描いてもらうというコミュニケーションを行いました。
自分は伝える側に選ばれましたが、図形という相対的な状況を言葉にする難しさや人に何か伝えるとき情報は注意深くしていないとかなりの部分が削ぎ落とされるんだということを突き付けられました。
大部分は聴講だったものの初日はこのくらいでした。
二日目について、この日は主に新人によるプレゼンがメインだったと思います。
各人のプレゼンの内容はどれも聞いている分には面白そうな内容でした。
初対面の人間相手ではなかったこともあり、自分のプレゼンはさほど緊張しなかったです。
途中、別のワークショップとして工数見積もりの演習を行いました。
頼まれたタスクに対して、おおよそどの程度で結果を出せそうかを見積もる、これも普段の研修だけでは磨くことのできないスキルだったと思います。
最終日について、この日は課題に対して考え得る解決策に様々な考慮を加えてからその策に順序付けを行うワークショップでした。
そもそも解決策を考えるのが難しい課題であり、考慮が深くなされているか、順序付けは他人を納得させられるだけの根拠があるかなど研修中で最も多岐に渡る思考が要求されるものだと感じました。
発表時に議論に参加していない人間から初めて指摘される考慮不足や提示される新たな策があり、複数人での作業であったものの議論の最中の発想や思考は閉塞していくものなんだと思いました。
研修の内容自体は以上でした。
今後、プログラミングスキル以外のスキルも要求されることは何となくは理解しているものの実際に何が要求されるか、その断片を知る良い機会になったと思います。
また、研修に付随する感想として、まず研修先の施設がかなり綺麗なところでした。
ちなみに部屋は同期との相部屋ではなく、各人に与えられていました。
食事についてもかなり満足でした。
単純に保養目的で個人的にまた行きたいなと思える施設でした。

2018年度入社 S.W
普段はプログラミング技術の向上を主とした研修をしているのに対し、合宿では技術以外のことを学ぶ研修だった。
普段の研修では学ぶことが出来ない内容も多く、得られたものも多かったと思う。
書籍プレゼンは準備期間があったこともあり、それなりに上手く出来たが、工程数見積もりは難しく、実際に業務で行う時に上手くやれるか不安が残る。
グループワークも思ったより上手く行かず苦労したが、最終的には上手くまとまったと思う。
合宿場は交通時間さえ考えなければすごく恵まれていたと思う。
部屋も綺麗だし、料理も美味しかった。
また合宿中に先輩社員の方々とも交流ができ、色々な話を聞けたのでよかった。
充実した3日間だったと思う。

2018年度入社 K.S
合宿の大きな柱は「7つの習慣」「書籍プレゼン」「見積もり方法」「課題解決手法」の4つでした。
「7つの習慣」では、ビジネスや日頃の行動に関する「当たり前だけど、それゆえに深く考えてこなかった」ようないくつかの習慣について、より深く考えたり異なる視点から見たりしながら考えを深めることができました。
「書籍プレゼン」では、事前にプレゼン資料を作成し、レビューを受けることを通して、プレゼンソフトの使い方のみならず、聞き手の立場に立ったときにわかりやすいプレゼンの行い方を学びました。
また、当日は他の人の発表を聴くことで、各自がどのようなことに興味を持っているのかを知り、興味深い知識を多く得ることができました。
「見積もり方法」では、あるプログラミングのタスクをどの程度の時間で完了できるかを見積もりました。
普段の研修では見通しを持たず漠然とプログラムを書いている場合が多いことに気づかされるとともに、実際の業務で使われる見積り技術の一端を見ることができました。
「課題解決手法」では、日常生活や業務上の課題について、決められた時間内で解決策を話し合い、提案をまとめる練習を行いました。
短い制限時間内で質の高い話し合いを行うための手法をいろいろと学んだので、今後の業務の中でも役立てられそうな気がします。
以上のように多くのことを学んだ研修でしたが、それに加えて使用させて頂いた宿泊施設が素晴らしかった(とても新しく、部屋が広く、料理も豪華でした!)ことも最後に付け加えておきます。
4月末時点での感想

2018年度入社 T.K
研修課題が難しいと思った。
多少Javaは知っているつもりでいたが、抜けている基本的な知識が多くあった。
ただ構文を覚えてコーディングするのではなく、その時に何が行われるのか・いつそれを使うのかなどを考える姿勢が身についたと思う。
Javaに限らず、どの言語を学ぶ上でも必要な姿勢であると思った。
また、一人でプログラムを書くのとは違い、同期レビューを通して同期と課題について話をすることで、より自分の理解が深まる気がしている。
自分の思い込みのまま終わることが少なくなるので、非常に有意義である。
今自分に感じている課題は、同期レビューに関して同期のコードを読むことがおざなりになってしまうことである。
他人の書いたコードを読むのが難しい。
同時に読みやすいコードを書くように心がけようと思った。
苦戦していたGitは少しずつ慣れてきた。
以前よりもGitのイメージが掴めるようになり、Gitの利点や使いどころが分かってきたと思う。
あとは操作コマンドやオプションなど、使いながら覚えていきたい。

2018年度入社 Y.I
入社してついに一ヶ月が経とうとしています。
プログラミング未経験での入社というのが少し不安でしたが、特に一人取り残されるといったこともなく研修に励めていると思います。
実際、入社後研修が始まってみて、毎日新しい知識が蓄積されていくのを感じています。
概念的に難しいものがあるなぁと思う反面、楽しくもあるのが現時点での研修に対する感想です。
研修中なのでまた印象が変わる可能性はあるにしても、学生時代に漠然と考えていた「社会で働くことは無味乾燥としている」といった感じもなく過ごせていると思います。
ただ、現時点での研修は課題に対して調査を繰り返してJava、ひいてはプログラミングを知るといった感じの研修なため、課題をこなすことが目標でありその先の目標がよく見えない事に一抹の不安があると言えばあるといった感じです。
社内の雰囲気に関して言うと、学生時代にネットの情報から漠然と想像していた「社会の人たち」のようにギスギスした感じではなく、近過ぎず遠過ぎずと言った印象です。
業務中はあまり先輩社員への質問は出来ていないのですが、メンター制度等で課題の内容や現状を報告する機会もあり、気分転換でもあり良い刺激にもなっています。
懇親会等で業務から離れたところではフランクな会話をする機会もあり、催し物が好きな自分としては今後も積極的に参加していきたいと思います。
総じて、現状は肌に合う会社だなと感じています。
生活面では、まだ欲しい家具も揃えきれていないので当面は家の内部を住みやすい空間にすることを目標にやっていきたいと思います。

2018年度入社 K.S
Javaはほぼ未経験の状態からのスタートでしたが、1か月でだいぶ遠いところまで来た気がします。
研修は、与えられた課題について調査し、理解したことをもとにプログラムを実装し、同期や講師のレビューをうけて修正する、という繰り返しで進んでいます。
多くの場合、課題を見た瞬間には何をすれば良いのかもよく分からないのですが、調査するうちにだんだん全体像や進むべき方向が見えてきます。
そして課題を完成させているとたいてい途中で大きな疑問にぶつかるのですが、Webページで調べたり手元で実験したりを根気強く続けていると、やがて全てが繋がってスッと腑に落ちる瞬間が訪れます。
この1か月でそんな瞬間を数え切れないほど経験できたので、充実感が強いです。
2017年入社
入社1年後の感想

2017年度入社 K.U
今年の4月で5ヶ月の研修と、7ヶ月の案件分働いたことになる。
この感想を書くにあたって、とりあえず過去の感想を見返してみた。
どうやら研修の始めの頃はGitの扱い方が分からないので詰まったりしていたらしい。
この件に関しては、さすがに研修初期よりは上手くなったはずだが、Gitの失敗で案件に迷惑をかけたことが少なくとも2回ほどあったので、今も克服するべき課題だと認識している。
一方アルゴリズムのロジック部分はすぐ書けるというのは案件でも変わらず活きていて、ロジックが思いつかないという止まりかたは無く、止まるにしても2択で迷うとか、その程度である。
この点は人より抜けている認識があるので、Git等でミスった時の心のよりどころになっているため、大切にしていきたい。
まぁこういった感じで、苦手を大きく克服することもなく、成長としてはいびつなレーダーチャートがちょっと大きくなった感じではあるが、この1年間考え方の面で思うことがたくさん得られた点は、今後のためにもとても良かったと思う。
具体的な例としては、考え方の本質的な部分だと「自分の本当の姿は論理派な人間ではなく、理論的なアウトプットが必要な時に適宜理論を構築するだけの、超感覚派の人間だ」とか、身近な部分だと「電化製品の触りかたを理解する際には、適当に押してみるみたいな賭けをせずに説明書を読むタイプだ」とか、こういった大小さまざまな知見が得られた。
後者とかは一見業務と関係無いかもしれないが、外部ライブラリを参照する際や、インフラ関係を触る際、そもそも分からないことを調べる際などに、どういった方針で理解に至るのが自分に合っているかの導きとなってくれるので、非常に役に立っている。
こういった気付きを実業務に活かして、効率を上げていきたい。
まぁ上の方でまだGitで失敗すると言っている通り、苦手の克服には至っていないが、苦手である理由や、一般的なアドバイスが自分にとって的確かどうかの見分けかた、自分なりの効率良い解決方法の気付きとかが分かってきた
(はず)
なので、この調子で業務を続けていくと良いと思って、先ほどの文章を書いている。
あ、あと9月末の感想で食事を常に少し豪華にするとかは無しかなとか言ってたけど、けっこう豪華にしてたなぁ。
一応貯金は増えてるけど。
あともう1つだけ、お酒が苦手なんですが、空気中に蒸発したアルコールを吸い込むことはあっても、液体としては1滴も飲まずに1年間いられたのは非常に嬉しかったですねー。

2017年度入社 M.T
インタープリズムに入社してから2度目の春を迎えようとしています。
わたしは8月末に研修が終わり、9月から現場入りしました。
現場入りした当初は目の前のタスクをこなすのに必死で、ただひたすらにタスクに向き合っているだけでしたが、最近になってやっと慣れきたのか、これだけでは物足りなさを感じるようになってきました。
不安で仕方がなかったあの頃から比べると随分大きな心的変化です。
わたしのモットーは仕事の中に楽しみを見つけ、楽しむことなので、この一年で仕事を楽しむための土台を築くことができたのではないかと感じています。
これからはどう楽しみを見つけながら技術を磨いていくのか、それを探していきたいです。
案件配属1ヶ月後の感想

2017年度入社 K.U
これで実際の業務に就いて1ヶ月になった。
この1ヶ月は、研修ではあまり扱わなかった言語の兄弟のような言語を用いて、既存の機能に追加機能を実装するというような内容の業務を行っていた。
新しい言語や、既存のコードの方針に馴染むことは大変であるが、諸先輩方に質問しながら無事に(?)実装を進められているので、一応なんとかなっていると思う。
しかし、サーバーに関係するコードを扱っていた際に、既存のコードに馴染めていないことだけではなく、単純な知識不足や、開発ツールを使いこなせていないことから、バグの原因を見つけることにとても苦労することがあった。
これも諸先輩方のおかげで原因特定に至ったが、横で見ていても特定方法がよく分からなかったので、時間をかけて慣れていきたいと思う。
また、今までの研修は言わば1人での開発であったが、業務内容は、共同での開発であるので、共同開発の際のGitの扱いというのも非常に大変だった。
自分以外の手によって編集が加わるため、それを取り入れることや、編集の衝突が起こってしまうことは、共同開発の上では自然に起こり得ることなので、そういったことが起きた際の対処法に慣れたいと思う。
ちなみに残業は無かったです。
これが当たり前であってほしいが嬉しい。
それ以外の部分では、10月から同期5人のうちの1人の配属先が本社勤務から変わってしまうので少し寂しい。
あと研修が終わったので、採用サイトを見れば分かる通り給料が7万円ぐらい上がる。
食事を常に少し豪華にするみたいな生活水準を上げるような行動は取らない気がするので、2台目の3DSを買うみたいな感じで短期的に消費することはあっても貯金がメインになるのかなぁ。

2017年度入社 S.N
9月から本社での作業案件に配属され作業していましたが、10月からお客様の現場へ行くことが決定したため今月の中頃からは業務で使うC#等の研修をしていました。
実際の業務としてはほとんど出来ていない状況なので来月から本当の業務を行っていくという状況になります。
ただ短い間でしたが開発の現場を見られ、一人で書く研修のコードではない業務で書かれているコードを見られたことはとても貴重な体験でした。
コードだけではなく打ち合わせなど1つのものを皆で作っていく現場を垣間見られたことも同じく貴重な体験となりました。
実感したこととしては長い研修ではありましたがまだまだ知らないことが多く沢山学んでいかないことがあるということです。
言語についてはもちろんですが、それだけではなくプログラミングを支援する沢山のツールについて精通する必要性をとても感じました。
働く場所が変わることに緊張していますが来月からはInterprismの社員として恥ずかしくないよう頑張っていきたいと思います。
研修総合感想

2017年度入社 M.T
4月に入社してから5ヶ月、長いような短いような研修の日々が終わりました。
入社してからあっというまにこの日が来てしまいましたが、とても濃い時間を過ごすことができたと思っています。
この期間、JavaやHTML、js、DB、インフラと多種多様なものに触れてきました。
中でも一番長い期間扱っていたのはJavaでした。
Javaの基礎構文について贅沢なほどに時間を使って、とことん研究を行っていました。
この経験があったからこそ、今から他の言語を始めようと思ったらどんなところが違い、似ているのか、そういった目を持って向き合うことができる気がしています。
また、HTMLやCSS、jsとJavaとは一風変わった言語に触れ、DBという根本から覆すような構造を持ったものに触れました。
たったの5ヶ月ですが、入社当初と比較すると随分と視野が広がり、この世界の幅広さを知りました。
研修においては、実に様々なことを学ぶことができたと思いますが、この幅広さを知ってしまった今、自分にはまだまだ足りないものだらけだと感じさせられています。
研修が終わってもなお、これの経験をもとに知識を集める努力は続けていきたいです。

2017年度入社 K.U
研修が今日で終わる。
Javaの基礎(むしろ最初はGitやIDEAの使い方がメイン?)に始まり、Javaに入っているAPIを用いたり、HTML、CSS、JavaScript、MySQL、インフラと、様々な分野の課題に取り組んだ。
自分はアルゴリズムに関しては事前知識があったので、マージソートを書く課題等は特に調べずに一気に書くことが出来たが、インフラの課題はいくら調べても自力ではどうしようもなかった。
4月の入社した頃と比べて成長したのは間違いないが、このように、どんどん出来る得意な分野や、手のつけようがないほどに苦手な分野がはっきり分かった点が良かったと思う。
これから実際の業務を行っていくわけであるが、Java等、既に自分が使ったことのある言語で、アルゴリズムの知識や、発想を問われるような分野なら、好きな分野なので嬉しいし、入社1年目の自分でも価値のある働きが出来ると信じている。
しかし、インフラ等が絡むと会社が人件費の名目でお金をドブに捨てているかのような気持ちになってしまう気がする。
実はもう配属先は決定しているが、まだ具体的に何をやるかは(内部的には決定しているかもしれないが、)知らないので、最初ということもあり、自分の手のつけられない分野の案件ではなく、自分の得意を活かせるような仕事を与えられたら良いなと思う。
新人5人が、現状全員本社にいるようなので、そういう寂しさは無いが、本社内単位での席替えにより、5人で居た島が無くなってしまいそうなので、少し寂しさを感じる。

2017年度入社 N.K
今日で研修が修了するが、知らないことを多く学べたとともに、これだけ多くの時間を学習に割けたのは非常にありがたいと感じた。
そしてこの研修の期間は非常に有意義なものとなったと感じている。
その理由としては、多くが耳にしたことはあるが使ったことはない技術であり、それを学ぶという真新しさがあったこともあるが、課題を通して学んだそれらの技術に対して、レビューを受け理解が正しいか、良い書き方となっているのかという、フィードバックを受けることができたというのが一番の理由である。
また、研修では技術的なことだけでなく、同期との交流が盛んに行われたため、同期との親睦を深める良い機会となったという点においても良い機会であったと感じている。
しかしながら、これまではあくまでも研修であり、研修を通じて色々な知識は身につけられたと感じているが、実際の現場でそれを活かしたことはないので、現場でそれらの知識を活かせるのか、貢献できるのかということに関しては結構不安が残っている。
新人研修合宿の感想

2017年度入社 A.S
普段の研修ではひたすらJavaの課題に取り組んでいるのですが、研修合宿ではビジネスよりの話であったり、自分の目標であったり、他とのコミュニケーション手法であったりと、Javaには関わりのないことについて学んでいきました。
どれも今まで学んだことのないものばかりだったので新鮮に感じ、また多少なり演習を通じて身につけられたと思います。
印象に残ったのは見積もり演習とテキストコミュニケーション、またプロフェッショナルについてです。
見積もり演習については結果の確からしさは一旦置いておいて、何の要素をどのように組み込んでいくかに関しての話が多かったように感じます。
演習自体は、身近な課題に始まり全くの未知の分野についての見積もりについてまで演習があり、非常に考えやすくなるよう組まれたものでした。
実際
そのおかげで自分の速度さえ把握することができれば概算は立てられるのではないか、というところまで来ることができました。
テキストコミュニケーションでは二派に分かれる内容についてflashを用いて議論しました。
その際にこちらに相手を怒らせるような意図がなくとも受け手によってはイラッときてしまう、しかしそのために時間を割いて長々と文章を書くには時間が足らず、、ということがないようにどのようなことに注意したらよいかなど知ることができました。
やはり先輩方の文章等見ると参考になることが多く、とても勉強になったと思います。
プロフェッショナルについては自分が思うプロフェッショナルを述べ、他者の意見を聞き、さらに自分のプロフェッショナルについて考えてみる、といった内容だったのですが、同期含め皆考え方に多様性があり非常に参考になりました。
また先輩方の思うプロフェッショナルについても聞くことができ、自分がまだまだ視野が狭いことを感じました。
いずれの研修でも、やってみると今までは気がつかなかったところで惑うことが多々あり、それぞれに対してより多くの範囲をカバーできる今後の指針となるようなレビューをもらうことができ、とても為になったと感じています。

2017年度入社 N.K
一番の感想は普段の研修で行ったことの内容ばかりであったので、新鮮であったということである。
1日目に行った7つの習慣では、当たり前だなと感じる部分も含まれてはいたが、逆にその当たり前のことをこなせれば成功に近くということを知れたため、成功するのに特殊な何かは不必要であるということを理解する良い機会になった。
2日目で特に印象に残った研修は、言葉のみで内容を伝える限定コミュニケーションと作業工程の見積もりを算出する見積もり演習である。
限定コミュニケーションでは言葉のみを用いて絵柄を伝え他の人にその絵柄を書いてもらうということを行った。
この研修を通して学んだこととしては、言葉のみで物事を正確に伝えることの難しさと、人によって物事の捉え方が異なり、その捉え方によって伝達する内容も異なってくるとうことである。
作業工程の見積もりでは、特定の業務を遂行するのにかかる日数を算出するという研修を行った。
この研修では、知識のない業務に関して、各作業にどの程度の時間がかかるのかを定量的に見積もることの難しさと大変さを体験する結果となった。
3日目は、問題解決を主に行った。
この研修では、問題に対する解決策を提案し、それらの中からどの解決策が最もふさわしいかを定量的に評価するという作業を行い、現状と理想の状態の把握や、解決策の評価など様々な段階に限られた時間をどのように割り振るか、どのような値を用いて評価するかといったことを決めるのが非常に難しく感じた。
他にも、同期や先輩の方々と多くの時間を過ごすため自然と打ち解けられ、知らなかった一面を知れたりと仲を深める機会として非常に有意義であったと感じた。

2017年度入社 S.N
普段のプログラミングの研修とは違い、皆で意見を交わしあう研修がほとんどであった。
比較的座学中心であった、「7つの習慣」に関する研修であっても付箋を使って議論をした。
一番印象に残り、大変だと思ったのは最終日にあった問題解決手法という研修で、2グループに別れ与えられた問題に付いて解決策を議論してまとめるものである。
はじめは自由に議論し自由な結論を発表したが、2回目からは与えられた方法で議論を展開するのだったが制限時間の40分を過ぎても結論を出すことが出来ずに終わってしまった。
そこから学習し、最後の議論ではなんとか結論まで達することが出来た。
難しかったのは解決案をコストや効果、実現容易性で具体的な数字で評価し、説得力のある結果を導くことで、そこに困難とそういうものが大事なのかぁという関心を抱いた。
その他の研修も自分に足りないものを多いに感じさせてもらえる研修が多くとても充実していた。
また同期、上司・先輩とともに食事をしたり必然的にコミュニケーションをとれたことも非常に楽しく感じた。
5月末時点での感想

2017年度入社 K.U
研修は、GitLabでforkした研修プログラムを少しずつ進めていって、mergereqestを承認してもらって成果をmergeするという形式で進んでいく。
研修の始めの頃は、Gitの扱い方が分からないので詰まったりだとかで、コードが分からないというよりはコードを管理する道具の使い方が分からないために止まってしまうということがあった。
今でも上手く使えてるとは全く思わないが、これをするとミスをする可能性があるからやらないという判断はつくようになり、滞ることが無くなったので、成長を感じる。
本題のコードを書くという部分について、学生時代に触れていた、アルゴリズムのようなロジック部分に関しては、サクサク進んでいたが、業務に使うJavaとして、言語の機能や性質、作法等については、非常に学習に苦労した。
研修当初の無いに等しいJavaの知識から、2ヵ月の研修によって、ある程度の内容は分かる状態まで来ることが出来たので、このまま研修を進んでいって、ちゃんと業務に就けるような状態になれれば良いなと思う。
同期は自分を含めて5人で、最初はみんな人見知りなのか、あまり会話が無かった。
しかし時間が経つにつれて、週に1回ぐらいのペースで昼食を一緒に行ったりとか、業務の質問以外の会話も増えてきたので、人見知りなりに仲良くなってきたと思う。
5月末~6月には、3日間の新人向けの合宿が用意されていて、現在は合宿の最中だが、昼食夕食を先輩2人を含めた7人で食べたり、性格が見えてくるような研修プログラムをこなしたり、夜に先輩の部屋で飲み会(お酒が飲めないのでお茶とカルピスを飲んでいたけど)をしたりすることで、先輩2人も含めて、より距離が縮まったと思う。
事務所での研修・合宿の残りの日・グループでの勉強会での発表と、現在取り組んでいることは色々あるが、それぞれこなしていって、一人前だと自分でも思える状態で研修期間を終え、業務に就けたらなと思う。

2017年度入社 M.T
4月の入社以後、Javaの基本から入り、APIの利用を勉強してきました。
入社前のプログラミングは初心者を抜け出す程度にかじったつもりでしたが、基本とされる部分でも新たに学ぶことが多くあり、自分の無知を思い知らされました。
本社での研修は自習形式で、わからないことがあれば、自分で調査をし、ときには同期と相談するなどして、理解を深めていきます。
実装までの道が明示されていないということもあり、未知のワードや領域などが現れると迷子になることもありますが、この迷子から得られる知識も多くあります。
このように自分で試行錯誤することで自分が成長しているように感じています。
また、各々が理解したことを実現するためにプログラムを書いていることもあり、目的の仕様を実現するために、一人一人が異なるアプローチで実現していることがあります。
ここが複数人でプログラミングを行う面白さであり、そして新たな学びへと繋がる一つの鍵だと感じています。
入社当初と比べると書くプログラムの規模が徐々に上がってきており、それに伴いアプローチの仕方に多様性が出てきています。
この多様性を利用して自分の知識を広げていけたら、知識が積もってのちに大きな力になると思います。
自分の調査により理解を深めるのも大事ですが、他と比較をすることでさらに知識を広げていけるよう、今後も頑張っていきたいと思います。

2017年度入社 S.N
率直な感想としてはもう2ヶ月経ったのか!という感想です。
入社してからしてから毎日課題をやり進めていますが入社してきたときに思っていたより意外に手強く進みが遅いと思います。
大学時代にJavaに触れていて最初こそ簡単だと思っていたものがAPIについてより深く考察する機会をもらったり、きれいなコードとはどういうものかを教わることで結構な時間を使わせて貰っている状態です。
そうこうしているうちに2ヶ月があっという間に過ぎました。
その間、毎週のKPTや合宿などでプログラミング以外の部分での研修も受けさせてもらっていました。
人と議論をしたり、協力して物事を進めていくことの難しさ、その上でどうやっていけばいいのかということを教えてもらいました。
同期ともはじめのよそよそしい空気からそのような研修を経て会話する機会も確実に増えたと感じます。
同期とは研修修了後勤務する場所がバラバラになってしまうので、もっとたくさん色々な話をしていきたいと思います。
10月までの研修はまだまだ続くので、もっと勉強しておけばという後悔が少しでもなくなる様に毎日頑張って行きたいと思います。
2016年入社
入社2年後の感想

2016年度入社 M.N
入社して3年、私はグラフDBを用いたシステムの開発に携わっています。
既存のシステムをグラフDBを用いるように書き直す仕事もありました。
自分ではない他の人が書いたコードは、意図を読むのが大変だったり、複雑に入り組みあって読み解くのに苦労することもあります。
しかし、実際に紐解いてみると新しい発見が出来たり、より良い書き方を教えて貰ったりと、良い経験になりました。
既存ライブラリにも不具合、バグを発見することも多いです。
そういう場合はIssueに報告したり、フォークして修正した上で用いたりするようなこともありました。
コーディングに関しても最近は手慣れてきた感じがしています。
以前まではインタフェース、抽象クラスなどはそこまで用いてなかった気がしますが、今ではまずそこから考えるようになりました。
まだクラス設計という点では未熟な部分があると実感しています、これからもっと沢山コードを見て、様々な知識を増やして、より良いコードを書いて行きたいです。
話は変わりますが、数学部の活動に参加しています。
数学はかなり久しぶりでしたが再びやってみると楽しいです。
新しいこと、やったことでも思い出せないことが多くあると思いますが少しずつ理解を深めて続けていきたいです。
入社1年後の感想

2016年度入社 S.K
私は研修が終わった後、1月から客先常駐で仕事をしていて、Webアプリのフロントサイド開発を担当しています。
仕事としてやることは、「分からないことを調べ、理解して実装する」という点で研修と変わらないと感じます。
そして、これからどのようなタスクをするにしてもそれは変わらないでしょう。
私は特に、わからないことを調べて理解するまでが苦手です。
私が1時間調べてわからないことを先輩社員に質問すると、3分くらいで答えにたどり着いたりして、能力の差を感じます。
研修でも、「分からないことを調べ、理解して実装する」をいかに早くできるかということを意識して行っても、良かったかもしれません。
(私はわからないことを納得のいくまで調べるという風に研修を行っていました。
それも大切だと思います。)
客先でのコミュニケーションについては、客先でのチームの人が人間的にいい人ばかりなので、人間関係ではストレスなく過ごせています。
ただ、自分の能力の低さのせいで迷惑をかけていることがある種のストレスになっているので、日々もっと仕事ができるようになりたいと思っています。
また研修が終わってからは、社内のグループに所属するようになりました。
グループでは、飲みに連れて行っていただいたり、数か月に1回集まって会議をしたりしており、新たな社内コミュニケーションが増えたと感じています。

2016年度入社 Y.U
入社してから1年が経ちましたが、その内訳は主に、研修が6ヵ月、現場での常駐業務が6ヵ月、となっています。
4月に新入社員が入ってきた自社ではもちろん、プロジェクト内でも、もう新人感覚ではいられないといった雰囲気が出てきております。
1年前の僕と今の僕との間にある差は、0と1との差です。
研修では"網"を張りました。
細い糸の、目が粗い網です。
そのうちの"プログラミング言語の部分"に、現場で使っているjsだとか、phpだとかがぺたぺたと張り付いてきて、"Gitの部分"には「共同開発」だとか「branch運用」の様なものたちが引っかかってきます。
そうやって様々なことが少しずつ身になって、より良い網が出来上がっていくのを感じています。
現場以外の活動でも、アドベントカレンダーで遺伝的アルゴリズムが張った部分に、勉強会でDeepLearningが張り付いたり、グループ会の、Unityを使ったゲームの共同開発で、C#や「Git運用」がくっついたりしました。
そんな0から1への1年でしたが、その差を侮ることなかれ、自信を持ちたいと思いつつ、自惚れることなかれ、新入社員に追い抜かれないよう、精進していきたいです。
研修総合感想

2016年度入社 Y.U
6ヶ月という研修期間は、短くあっという間だった、とは言えず、十分に長かったと思っています。
プログラミングの課題だけなら、もっと早く(もっと効率良く)終わらせる方法もあったと思いますが、その効率の良さを模索する事や、時間的には大幅なロスとなっていた同期間の相互レビュー、KPTは必要なものであったと思います。
長かったと言いましたが、プログラミング、あるいはコンピュータについての知識を身につけるという意味では、6ヶ月はあまりにも短すぎたと言えます。
4ヶ月間もの時間を使って比較的じっくり取り組んだJavaでさえまだまだ知らないことは多く、プログラミング言語には他にも様々なものが存在します。
それらのうち幾つかは必ず触れるものであり、実際に今は案件でJavaScriptを使っています。
深い”仕組み”への理解は足らず、基礎的な文法から調べる事もありますが、確実に学べていて、使えています。
6ヶ月の研修で身についたのは、そういう力だと思っています。

2016年度入社 Y.Y
新人研修は課題が出され、それを解くという形で行いました。
私はプログラミングの経験がほぼありませんでしたが、課題に必要な知識を調べ、疑問に思ったことを実験し、何度もレビューを受けることでプログラミングスキルを身につけることができたと実感しています。
特に上司からレビューを受ける、または同期間で相互レビューをすることにより、ただネットや書籍を見るだけでは気づきづらい可読性、外部依存性などの不備に気づくことができ、より実践的なスキルを身に着けることができたと感じています。
課題の内容に関しても、基礎的な知識からアルゴリズム、APIの中身、ファイルIO、HTML、CSS、JavaScript、データベースにインフラなど、多種多様な課題があり、幅広く知識を身につけることができました。
また、ただプログラミングについて学ぶだけではなく、毎週行われるKPTや、4月に行われたビジネスマナー研修、5月末に行われた新人研修などで、ビジネススキルについても学ぶことができました。
半年という一般的な研修と比べて長い期間でしたが、学ぶ内容が多く日々新しいことを学べてので、気持ちが緩むことなく、充実した半年間を過ごすことができました。

2016年度入社 S.K
研修ではJava、HTML、CSS、JavaScript、MySQL、インフラについての課題を行った。
Javaの課題は最初の4か月間行った。
一つの言語を習得することで、ほかの言語の習得がしやすくなるため、時間をかけるとのことだった。
実際にJavaの研修課題で得たものとしては、Javaに慣れてある程度書けるようになったということもある。
しかし、ほかの言語にも応用できるような(今まで思いつきもしなかった)基礎的な考え方(可読性やオブジェクト指向、型、型がプリミティブとオブジェクトに分かれている理由、JVMというものの存在、メモリ空間…etc)を学ぶことができたことが大きなメリットだった。
また、実際に実装をして学ぶことは深い理解につながるので良いと思った。
例えば「http通信を行い」という文章を見たとき、その背景の仕組みを具体的に想像できるのは、自分で実装を行ったからであると感じる。
そして、4か月学んだ結果、学ぶべきことの多さと難しさにおどろいた。
4か月かけたからJavaの基礎的な部分を理解できたかと言えばそうではなく、ポリモーフィズムやインターフェースの使いどころ・意味、ガベージコレクションなどまだわからないことや実感を持って説明できないことがまだ多くある。
Javaの後は、HTML、CSS、を2週間、JavaScriptを2週間学んだ。
言語ごとにある「思想」が面白いと思った。
インフラについては1週間学んだ。
何をしているのかあまり理解せずに行ったため、ぼんやりした内容だけで、力になっているのかはかなり怪しいと思う。
全体を通してよかったと思うことはまず、Java、HTML、CSS、JavaScript、MySQL、という言語を学びながら、(API・ライブラリなどといった無数にあるわからない単語・意味や、Gitやサーバ、ネットワーク、環境構築など)プログラム言語ではないが、作るもの・やろうとしていることの全体像を把握するのに必要な知識を知ることができたことである。
プログラム言語を書けるというだけでなく、それが影響する様々なものの知識と動かし方を知らないと何もできないということを知ることができたのでよかった。
そして、何もわからないことを素早く把握する能力が必要だということがわかったこともよかった。
課題に取り組むときは、問題文の単語が一つもわからないので、その単語の意味を調べるところから始まるが、その単語を説明している分の単語がほとんどわからないというループになることが非常に多かった。
全体像が見えてない中でどれが理解するべき単語、もしくは概念で、どれが意味を分かる必要のないことなのか、理解するべきことでもどの程度の深さまで理解するべきなのかを判断することは難しかった。
その調べる能力(すぐに理解する能力)は、仕事ができるできないに直結するので、調べる練習にもなったと思うし、なにより難しさがわかったことがよかった。
新しいことをできるようになるには高い学習コストがあって、研修ではバックエンド、フロントエンドを広く薄くやったが、まだまだ知らないと土俵に立てないようなことがたくさんあると感じているため、理解できることの幅を広げていきたいと思う。
研修システムの改善点としては、HTML、CSS、JavaScriptに関してはよく知っている人がレビューしたほうが得るものが多いと感じた。
新人研修合宿の感想

2016年度入社 Y.U
1日目の「7つの習慣」と2日目の「書籍プレゼンテーション」で、普段あまり読まないビジネス書籍とその考え方について触れることが出来ました。
どれも新鮮に感じる事が出���、1つの知識として自分の中に収める事が出来たと思います。
「コミュニケーション」や「メッセージング討論」、「課題解決手法」ではビジネススキルを身につけるとともに、その必要性について考えさせられました。
特に「課題解決手法」では、限られた時間の中で結論を出すために、半ば無理矢理かつ恣意的な設定を用いたにも関わらず、意外に納得できる結論を出す事が出来たので面白かったです。
「エンジニアキャリアケーススタディ」、「プロフェッショナル」はエンジニアとしての考え方に触れることが出来ました。
青木さんや平野さんから現場の話を聞く事も出来ましたし、プロフェッショナルでは自分の現時点での目標を決める事が出来ました。
この時間は特にですが、3日間を通して、非常に有意義で楽しい時間になったと思います。

2016年度入社 M.N
普段の研修はひたすらJavaのプログラムの課題に取り組むことが多いですが、新人研修合宿はコミュニケーショントレーニングや自分自身を見つめ直したり、7つの習慣に関しての講義など普段や
らないような学びがあって新鮮でした。
特にプロとは何かということを考えたことがためになりました。
個人的には、趣味でプログラミングをしたり、趣味でヴァイオリンを弾いたりしていた頃
から趣味であっても何に関してもプロになりたいという意識を持って全力で取り組もうという考えで、プロは完璧に物事をこなせるみたいなイメージで居ましたが、同期の他の方のプロに対する違った価値観、例
えば責任感がある、時間を厳守するなどを聞いて少し自分の中のプロ像が変わった気がしました。
双方伝達のコミュニケーションでも一方的な伝達より、いかに相互に議論することが効率的で理
解もしやすいかが分かり興味深かったです。
複数が同時に議論するテキストでの議論は難しく、練習が必要だと感じました。
今後のためにも非常にためになる合宿だったと思います。

2016年度入社 Y.N
テキスト討論というプログラムが印象に残りました。
意見が割れる議題を選んで、話さず、メッセンジャーだけを使って議論します。
相手の不快を避けながら、どうやってスムーズに自分の意見を主張するか、これは実践してみると難しかった。
自分に怒らせる意図はないのですが、テキストの受け取り方次第で相手がカチンときてしまう。
かといって、主張を選び、言葉を選びしていると、あっという間に議論が進んで、脱落してしまう。
ともかく、思っている通りに手と頭を動かして、テキストを操るのが難しい!監督兼参加者のマネージャ二人はさすがに手際よく、大変勉強になりました。
相手に同調しながら自分の意見を並べて主張を抑える、議論の交通整理などなど、今まで省みなかった技術や知識が新鮮でした。
また、自分の考えを文章にして出力する速度が致命的に遅いと気づきました。
これは合宿一番の教訓です。
もう一点良かったと感じるのは、入社同期内でコミュニケーションが活発だったことです。
コミュニケーションといえば大げさですが、プログラム内での発表、発表以上の個々の意見、さらに外側にある雑談、とにかく話す機会は多かった。
普段はプログラミングでそれぞれが計算機に向かっているので、なおさら貴重な時間に感じます(普段話せない規則はないのですが、皆集中しています)。
合宿はプログラミング技術以外の、考え方や伝え方、意思決定の仕方を学ぶのが目的でした。
正直今やれと言われても再現できないのですが、研修後の実務で思い出すだけでも役に立つ内容はたくさんあったと思います。
4月末時点での感想

2016年度入社 Y.U
この1カ月の研修では、まずJavaの基礎を確実に理解するように努めました。
抽象的な課題が多く、何をすれば良いのか分からない事も多かったのですが、自分なりの解釈の下で取り組み、その中で疑問が見つかればそれを調査するという、自由な姿勢で取り組めたのは嬉しかったです。
今は研修の第二段階に入り、アルゴリズムを考えています。
要求された仕様のプログラムを作る課題ですが、効率の良いアルゴリズムと可読性の高い分かりやすいコーディングが求められます。
コードが短く、効率の良いアルゴリズムであっても、分かりにくければ意味がないという事実を痛感している最中です。
しかし、効率と可読性の落とし所というのは大抵綺麗でまとまっていて、例えば変数の名前1つ変えるだけでそれが実現できる事を先輩に教えて頂いた時は感動しました。
頭を抱える事も多いですが、結構楽しんでコードを書いています。
2015年入社
入社2年後の感想

2015年度入社 W.A
私は、通信端末をweb上で販売するための画面を作成しています。
入社三年目、また、現在携わっている案件も三年目に入り、働き方が大きく変わってきました。
はじめの二年間は、会社の先輩方と同じチームで、細かい画面修正を中心に受け持ってきましたが、今年からは、現場でのチーム編成が変わり、先輩方と別のチームで働くことになりました。
また、現場の仲間からも、徐々にルーキー扱いされなくなり、今までとくらべて、画面のシステムの一歩奥の部分を任されるようになりました。
販売している商品の料金を修正する仕事は、
料金のデータの受け渡しの仕方を修正する仕事に代わり、内部向けのテストに新商品のデータを追加する仕事には、テスト自体をより厳しく、効率よく実行する作業が付随したことにより、私の働きぶりが、最終消費者だけでなく、現場全体の仕事のあり方にも影響を与えるようになりました。
これまでは、画面上の表示に間違いがないか、ということを注意して仕事に臨んでいましたが、今年からはより多くの要素を考え合わせて仕事を進める楽しさがあります。
今までの商品の入れ替わりの傾向から、将来、どのような画面表示の修正が加わるか予測し、
それを円滑に進められるようなシステムの構築、今後、チームに加わるであろう後輩が、より早く作業に取り掛かれるような読みやすいコード、ディレクトリ構成等といった、難しさの中にある面白さを、より深く探求して行きたいと考えています。
5月末時点での感想

2015年度入社 W.A
新人研修のJava入門では数多くの課題を通じてJavaの基礎事項を学んでいきます。
私はプログラミングの経験がなかったため、再帰処理を用いて○△※〜するプログラムを書け、という課題を与えられたときには、まず再帰処理とは何かというところから調べて、自力で学び、解答を作成していくことになりました。
時間はたっぷりと与えられますが、課題の量もそれなりに多く、はじめは圧倒されました。
しかし、目の前のわからないことを一つ一つわかるようにしていき、ゆっくりとマイペースで進めることで、楽しく学ぶことができています。

2015年度入社 T.Y
研修は課題が出されてそれを解いていくという方針で受けています。
もし、わからない所があれば、まず同じ研修中の同僚と相談して、それでもわからない場合は先輩や上司に質問しています。
課題提出後に一発通過出来ることはほとんどありません。
その後に修正箇所を指摘され、修正をする。
その作業を重ねることでより良いプログラミングが出来るようになっています。
私は他の同期の方々と比べて進みが遅いほうですが、それに関して特にプレッシャーを感じていません。
理由としては上司の方の「進む速度は人それぞれ、着実に歩む方が大事。」という話を受けたからです。
ですので自分なりの精一杯にてやらせていただいています。
現在はJavaの基礎の部分を学んでいます。

2015年度入社 H.K
毎年研修方法が変わっているそうですが、今年度の新人研修のJavaの基礎では「オーバーライドについて調査せよ」というような抽象的な課題が出され、各自必要な知識を調査・収集しながら問題を解く、というような形式で進行しています。
コーディングを伴う課題ではコードレビューを行ってもらったり、他の新入社員のコードを読んだり、文法の調査の課題では理解したことをまとめて先輩社員の前で発表し質疑応答したりと、他者の視点を得られる機会が多いです。
自分では気付かなかった考え方を学べるため、一つの事柄をより深く学べていると感じます。
技術研修以外では、他社と合同で行われる3時間ほどの新入社員向けビジネスマナー研修に参加させていただきました。
ビジネスマナーは研修だけでなく、日頃の業務で実践しながら身につける必要があると感じた一方、今のところ業務上で電話対応などの実践機会がないため、社会人としての基本スキルが身に付いているかという点では不安を感じています。
ここは、今後個人的に意識して改善していきたい点です。
研修を開始してからまだ1ヶ月半ほどでJavaにしか触れていませんが、日々プログラミングスキルが身に付いていることを実感できています。
新人研修合宿の感想

2015年度入社 W.A
合宿は日頃の研修で行っているコーディングとは異なり、グループワークやセミナー形式でした。
たとえば、「プロであるとはどういうことか」といったことについて意見を出し合いました。
この話し合いに関しては、参加者はそれぞれ異なる考えを持っていましたが、その意思を統一するのではなく、それぞれが持っている考え方を洗練する形で進められました。
自分の考えの矛盾点等を修正し、他の参加者の意見のうち、共感できる点については取り入れました。
逆に、意見を統一するグループワークも行われました。
たとえば、「学級崩壊を防ぐ方法」について話し合うという課題があり、与えられた手法をもとに、それぞれ意見を出し合い取捨選択するといった形で進められました。
入社してから最も自然言語を多く使った3日間で、慣れないことをして疲れましたが、非常に充実していました。



